お金を貯めようと思ったとき、「収入から余った分を貯金する(=余り貯金)」派と「収入を得たらまず一定額を先に貯金する(=先取り貯金)」派に分かれることが多いです。本記事では、両方式を多面的に比較し、あなたにとって効率的な選択をするためのヒントを提供します。
目次
- 方式の定義:先取り貯金と余り貯金とは
- メリット比較:どちらに強みがあるか
- デメリット比較:注意点と落とし穴
- あなたにはどちらが向いているか?適合性の視点
- 実践法:効果を最大化するコツ
- 心理的側面と行動経済学の観点から見る比較
- まとめ・結論と応用アドバイス
- 関連リンク(内部リンク)
方式の定義:先取り貯金と余り貯金とは
先取り貯金とは
先取り貯金(または先取り貯蓄)とは、収入が入った瞬間、またはその直後に、あらかじめ定めた一定額を貯金用口座や別の資産に移しておき、残った金額で生活する方式です。 この方式は、意図せず使ってしまって貯金できなかったという状況を防ぐよう設計されています。 実際には“給料天引き”“自動振替”“定期積立”などの仕組みを活用して、手間なく“先に貯める”仕組みを作ることがよく推奨されます。
余り貯金(残り貯金)とは
余り貯金とは、まず生活費・固定費・変動費を使い、その後に手元に残ったお金を貯金に回す方式です。 “使ってみて余ったら貯金”という考え方で、可処分所得をすべて使う可能性もあるため、計画が甘いと 貯金できない月が発生しやすいのが特徴です。
メリット比較:どちらに強みがあるか
先取り貯金のメリット
- 無意識の浪費を防ぐ 先に貯金分を“消してしまう”ことで、残る金額で暮らすしかなくなり、不要な出費を抑えやすくなります。 行動経済学で「手元に金があると使ってしまう」傾向があることはよく指摘されています(パーキンソンの法則類似の原理)
- 貯金が継続しやすい 貯金を“やるべきこと”に組み込むことで、後述する仕組み化が可能になり、貯金を忘れたり手をつけたりしてしまうリスクを減らせます。
- 目標に近づきやすい 毎月一定額を着実に貯めることで、目標達成の予測が立てやすくなります。不確実性が低くなります。
- 心理的安心感を得られる 「今月はもうこれ以上使えない」と明確な枠ができるため、浪費の罪悪感や後悔を減らす効果もあります。
余り貯金のメリット
- 柔軟性が高い 生活費や支出が変動しやすい人(フリーランス・歩合制など)にとっては、先取り貯金が負担になる可能性があります。その点、余り貯金なら収支に応じて調整しやすいです。
- ストレスが少ない感覚 “まず使ってから考える”という心理で自由度があり、貯金のハードルを意識せずに済む人には負担感が少ない場合があります。
- 臨機応変に対応できる 緊急支出・予備費の扱いが柔軟で、支払いがかさんだ月でも調整しやすいというメリットがあります。
デメリット比較:注意点と落とし穴
先取り貯金のデメリット・注意点
- 生活費が逼迫するリスク 貯金を優先しすぎて、日常の支出がギリギリになると、貯金分を切り崩す可能性があります。特に最初から多額を先取りしすぎると、手元が苦しくなります。
- 臨時支出への備えが必要 急な出費(病気・修理・冠婚葬祭など)に対応できないと、貯金を崩すハメになるので、予備費は別途確保すべきです。
- 過剰な金額設定は継続困難 あまり高額を最初から先取りすると、モチベーションが続かなかったり、節約疲れが来たりする可能性があります。
- 制度・仕組み依存性 自動振替や給与天引きなどの仕組みがないと、意識しなければ先取りがずれたり忘れたりする恐れがあります。
余り貯金のデメリット・注意点
- 浪費誘惑に弱い 手元にお金があると、つい使ってしまい、貯金どころか赤字になることも。貯金できない人の典型パターンです。
- 不安定な貯蓄額 毎月変動してしまうため、貯金がゼロになる月、予期せぬ支出が重なる月も生じやすいです。
- 目標管理が難しい 「今月どのくらい貯まるか」が読みにくく、計画性に乏しくなる可能性があります。
- 貯金優先順位が後回しになりやすい つい“欲しいもの”や“衝動買い”を優先させてしまうという悪循環に陥りがちです。
あなたにはどちらが向いているか?適合性の視点
「どちらがいいか」は人によって変わります。以下の観点から、自分の性格・収支状況に照らして選んでみてください。
性格・行動パターンでの適合性
- **浪費癖が強い・誘惑に弱い** → 先取り貯金が向く可能性高
- **変動収入・不安定な収支が多い** → 余り貯金の方が調整しやすい
- **ストレス耐性が低い/貯金制約に縛られたくない** → 余り貯金をゆるく始めて慣らすのも一手
- **継続力・計画力がある** → 先取り+見直し型、または余り貯金でも管理しやすいスタイルも可
収支・金額規模での適合性
- **余裕のある収入で固定支出が少ない** → 先取り貯金で侵食リスク低め
- **固定費が多い・生活余裕が少ない** → 最初は小さめに先取り、または余り貯金で調整する形式が安全
- **貯蓄目標が明確で月ごとに一定額必須** → 先取り貯金で定量確保が効果的
実践法:効果を最大化するコツ
先取り貯金を成功させるための具体策
- 無理のない金額から始める 最初から収入の30〜50%を先取りするのは現実的ではないことが多いです。多くの専門メディアでは「収入の1〜3割程度」が目安とされています。
- 仕組み化・自動化する 自動振替、定期積立、給料天引き、銀行の「定額自動入金」制度などを活用して“忘れないようにする仕組み”を作ることが非常に重要です。
- 貯金用途を分けて口座を使い分ける 緊急予備、旅行資金、大型購入用など用途別に口座を分け、目的が曖昧にならないようにします。
- 定期的に見直す 収入が増えたり支出構造が変わったりしたときには、先取り額を見直して調整を入れることが大切です。
- 緊急予備費は別確保 先取り貯金とは別に“すぐ使える予備資金(生活費3~6ヵ月分など)”を別枠で持っておくと、破綻を防げます。
余り貯金を効果的にするための工夫
- 支出管理を徹底する 家計簿や収支アプリで毎日の支出を可視化し、無駄を早期に発見・抑制することが肝要です。
- “最終ライン貯金”を設ける 例えば「月末の余りが2万円以上なら貯金」など、一定のラインを設定して貯金行動を強制する方式も使えます。
- 節約目標を設けてモチベーションを高める 「今月は交際費を5,000円以内」など予算制約を設け、そこから浮いた分だけを貯金するというルールも有効です。
- 先取り併用型にする 余り貯金方式でも、最低ラインだけ先取り(例:月に必ず最低5千円を先取り)しておくことで、ゼロ貯金を防ぐハイブリッド型も有効です。
心理的側面と行動経済学の観点から見る比較
アンカリング効果・参照点の設定
先取り貯金は「貯めるライン(目標額)」を明確化することで、支出行動に対する参照点を設定できます。対して余り貯金は、参照点が曖昧になりやすく、消費判断が揺れやすいです。
手元資金の感覚効果
“手元にある金額が少ない=ケチ感”を感じやすくなるという心理もあり、先取り貯金を行えば、必要な支出以外に手が出にくくなります。一方、余り方式では“余計な余裕資金”が誘惑を誘発しやすいというリスクがあります。
時間割引率・将来志向との関係
将来価値を重視する人(時間割引率が低い人)は、先取り貯金のように未来を優先する方式と相性がいい傾向があります。逆に“今を優先したい”という傾向のある人は、余り貯金方式に惹かれやすいでしょう。
まとめ・結論と応用アドバイス
以上を整理すると、以下のように結論づけられます:
- 浪費抑制力・確実性重視なら「先取り貯金」が有利
- 変動収入や生活の不確実性が大きいなら「余り貯金」またはハイブリッド型が安心
- 心理的・行動傾向も大きな影響を与えるため、自分のタイプを踏まえて選ぶことが重要
- 先取り・余りどちらの方式でも、仕組み化・見える化・見直しは不可欠
実際には、「先取り貯金をベースにしつつ、変動月は余り方式で補正する」など、融合型スタイルがもっとも現実的で応用が利きやすいことも多いでしょう。
まずは試しに1〜3ヶ月、どちらかの方式で運用してみて、実感を得たうえで微調整するのがおすすめです。

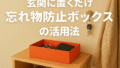
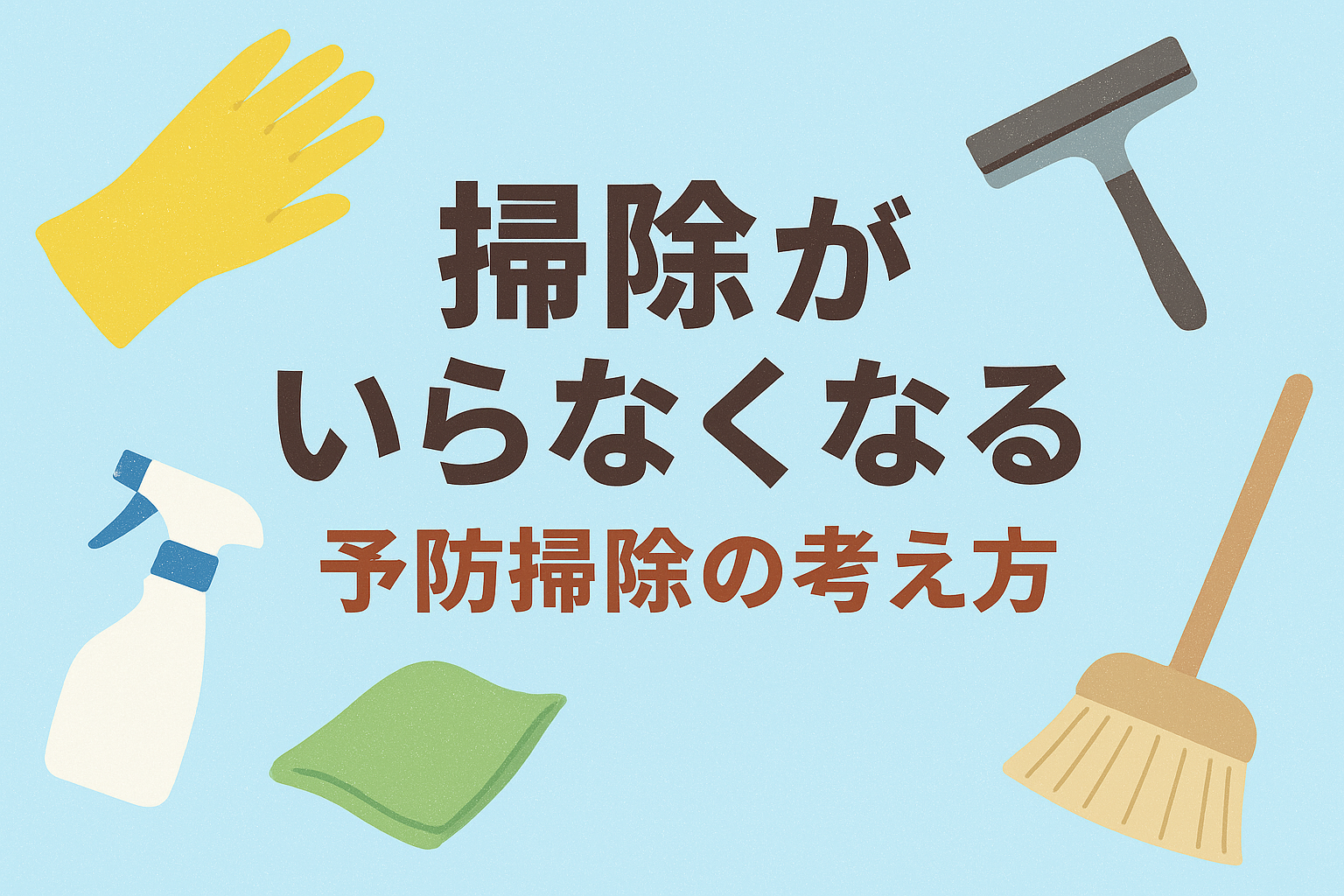
コメント