ちょっとした鍵・カード・小道具など、「置き場を失う小物」が家の中を乱雑に見せていませんか? 本記事では、「ワンボックス収納」という考え方をベースに、小物の定位置化と収納術を合わせて、“散らからない習慣”をつくる方法を詳しくご紹介します。 どこから手をつければいいか迷っている方、収納が苦手な方もステップごとに読み進めてください。
ワンボックス収納とは?メリットと考え方
「ワンボックス収納」とは、「ある範囲の小物を一つのボックス(箱・ケース・トレイ等)にまとめて入れる」 ことを原則とした収納スタイルです。必要なモノを「ひとまとめの場所」に集めることで、“あちこちに置かれる小物”を防ぎます。
このスタイルが有効な理由として、以下のメリットがあります:
- 小物の「迷子化」を防ぐ:出す・戻すがワンボックス内で完結する
- 視覚的なノイズを抑える:散在しないので空間がすっきり見える
- 習慣化しやすい:日常の動きの中に組み込みやすい
- 引越し・模様替えにも強い:ボックス単位で運べる・場所替えしやすい
この「ワンボックス収納」の発想は、身の回りだけでなく書類管理・ガジェット収納・子どもの小物にも応用可能です。 ただし注意すべき点もあり、適材適所で使い分けないと逆にモヤっとする収納にもなってしまいます。
ワンボックス収納を日常化する 4ステップ
以下のステップに沿って進めることで、小物が“散らからない習慣”に結びつけやすくなります。
- ステップ 1:仕分け → ボックスの設計
家中の対象とする小物(鍵・充電ケーブル・筆記具など)を一度一か所に出して、「カテゴリ分け」します。 この時点で「本当に必要なものかどうか」を見直すと、後の収納が軽くなります。 - ステップ 2:ボックスを選ぶ/揃える
仕切り付きトレー、仕切り板、引き出し式ボックス、フタ付きタイプなどを選びます。 サイズ・高さ・取り出しやすさを重視。透明タイプは中身が見えてしまい視覚ノイズになることもあるので、 半透明・カラー素材で統一感を持たせるのも有効です。 - ステップ 3:定位置化+ラベリング
ワンボックスをどこに置くか(机上、引き出し内、棚上など)を決め、周囲の動線を意識して定位置を割り振ります。 さらに、ラベルを貼る/テープで表示するなど、「どの小物がそのボックスに入るか」が一目でわかる工夫をします。 - ステップ 4:見直し/リセットの習慣化
1週間や1か月ごとに「本当に使っているか?」「余剰なものはないか?」を点検します。 使っていないものは手放すか別の保管場所へ移すなどのアクションをとります。これが“収納を溜め込まない習慣”をつくるコツです。
実践例:部屋別・場所別 ワンボックス収納術
以下は具体的な例。自宅の収納環境に合わせて応用してみてください。
① 玄関・エントランス
- 鍵・定期券・スマホをまとめる「玄関トレイ」:出入り時にここに置く習慣をつける
- 傘・手袋などの外出小物は、立ててしまえるボックスにまとめ、上下に収納
- 壁掛けボックス+フックを併用して、手が届きやすい位置に配置
② リビング・書斎
- リモコン・充電ケーブル・文具などを一つのトレイへ
- デスク引き出し内は、仕切り板入りトレイを使って「ペン類」「付箋類」など小分類
- 配線類はワイヤークリップや結束バンドでまとめ、ボックス内で束ねて収納
③ キッチン・家事スペース
- ラップ・輪ゴム・調味料小袋などを「調味小物ボックス」に
- 引き出し内に浅トレイを複数配置し、取り出しやすい配置に
- シンク下に引き出し式ケースを使い、「清掃道具」「スポンジ」「ゴミ袋」などを分ける
④ 洗面・浴室・洗濯周辺
- 歯ブラシ・綿棒・コットンをボックスにまとめて、置き場を限定
- 洗濯バサミや洗剤小道具も一箱にして、使う流れで出し入れ
- 洗面台下の扉裏にトレイを設け、細かい小物を収納
⑤ 子ども部屋・おもちゃスペース
- ブロック・小さな玩具などを透明ケース × 色つきラベルで分類
- お絵描き道具・カード類もひと箱にまとめ、出し入れしやすく
- 遊び終わったら“箱に戻す”というルールを子どもと共有
⑥ モバイル・ガジェット類
- スマホ・タブレット・モバイルバッテリー類をケーブルと一緒に収納
- 仕切り付きケースで「ケーブル長さ別・用途別」に分類
- 出張や持ち歩き用セットをワンボックスでまとめて持てるように準備
また、収納だけでなく「出し入れの流れ」「清掃しやすさ」も意識することが、長く綺麗を保つコツです。
長く続けるための注意点・コツ
ワンボックス収納を習慣化するには、以下のポイントにも気をつけましょう。
- 箱・ボックスの容量オーバーに注意:詰めすぎるとボックスが使いにくくなり、結局ゴチャゴチャになる
- 複数ボックスにまたがる小物は避ける:同じ種類の小物を複数の箱に分散させると迷子になりやすい
- 透明ボックスを多用しすぎない:中身が見えると散らかって見える。フタ付き・半透明タイプも活用
- 定期的な“見なおしデー”を設定:1か月に1回など、不要物を見つけて手放す時間を設ける
- 家族や同居人とルールを共有:収納場所・戻すルールを家族で統一しておくとずれにくい
- 最初から完璧を目指さない:まずは小さな領域(デスク引き出しなど)から始める
このような注意点を押さえておけば、ワンボックス収納は“続く収納”になります。
まとめと次のステップ
本記事では、小物が散らからない「ワンボックス収納」の考え方・手順・実践例・注意点を網羅的に解説しました。 まずは、今すぐ手をつけられる“最も乱れている1か所”から始めてみてください。定位置/ラベル/見直しを意識すれば、確実に「散らからない習慣」が育っていきます。
また、収納・整理の視点を広げたい方は、当サイトの 「シンプル収納入門—100円グッズで暮らしに“静”と“整”をもたらす」 もぜひ参考にしてみてください。
少しずつ改善しながら、自分なりの「散らからない暮らし」をつくっていきましょう。応援しています。

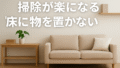
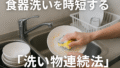
コメント